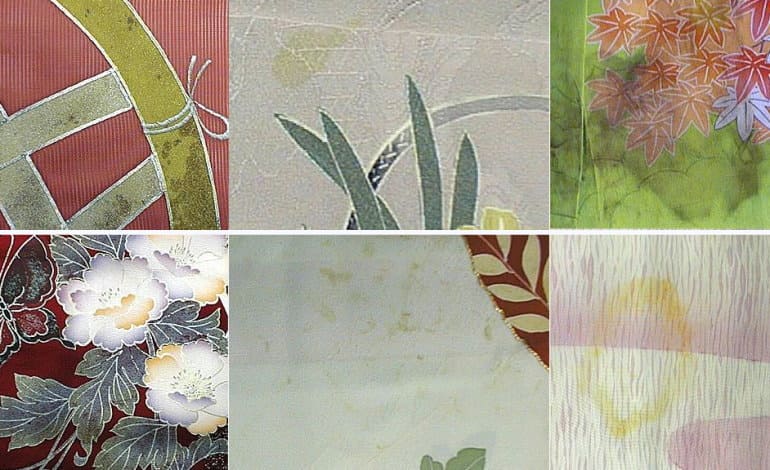着物に付く汚れには様々な種類がありますが、一般的には聞き慣れない言葉としては「混合性のシミ」が挙げられるでしょう。混合性の汚れは着物のシミの中でも独特な特徴を持っており、シミ抜き等の対処にも注意が必要となります。
着物の混合性シミに対して安易なシミ抜きを行った結果、汚れが繊維に残ってしまい、取れないシミとなってしまうことも…。

目次
着物の「混合性汚れ」とは?実例と特徴
着物についた「混合性の汚れ」とは、油分と水分の両方を含むシミのことです。これだけだとすこしわかりにくいので、実例をいくつかあげてみますね。
例
- ラーメンのスープの汚れ(背脂の油脂 + スープの水分)
- ドレッシングの汚れ(オリーブオイル等の油脂 + 酢や野菜汁・果汁等の水分)
- 焼肉のシミ(肉汁の油脂 + 肉のタレの果汁・野菜汁・醤油等の水性汚れ)
- カフェオレのシミ(乳脂肪分の油脂汚れ + コーヒーの水性汚れ)
なんとなくイメージが掴めたでしょうか?カンタンに言えば「水と油が両方入っているものが原因なら混合性!」ということですね。水ベースの製品の中に油が含まれていたり、油分ベースのものでも果汁や水分などが豊富に含まれている場合だと「混合性汚れ」の仲間に入ります。
混合性汚れには、次のような特徴があります。
水性汚れや油溶性汚れと間違えやすい
実際に着物についたのは混合性の汚れなのに、水性汚れと間違えられていたーーこんなケースは珍しくありません。例えば「スープで水っぽいから水性のシミ!」と思い込むのは危険。スープの中にバターや生クリームがたくさん使われていたら、油脂も多く含む「混合性汚れ」ということになります。
混合性汚れを見つけるには、プロによるキチンとした検査を行うか、汚れの原因をキチンと特定することが大切です。
油と水の両方のシミ抜きが必要
Tシャツ等の丈夫な洋服の汚れであれば、シミが付いてすぐに酵素入り等の強力な洗剤(アルカリ性洗剤)で洗うことで混合性汚れを一発で落とすことができます。洗剤の強力なパワーで、水性汚れと一緒に油汚れも分解してくれるからです。
ところがデリケートな着物に付いた混合性汚れの場合は、上のような洗濯方法ができません。シミの部分の油汚れをまず溶かして取り除いてから、水性汚れを洗って落とす…このような「二段階の汚れ落とし」が必要となります。
少し手間がかかってしまうのですが、後で汚れが残らないようにキチンと対処をすることが大切です。
着物の混合性汚れのシミ抜き方法
では実際に、着物の混合性汚れをどのようにシミ抜きするのか見ていきましょう。
事前の確認
着物の混合性汚れをご家庭で落とすには、含まれる「水性汚れ」を落とすための
水洗いのプロセスが必要です。ご家庭で水洗いができる着物かどうか、洗濯表示・製品表示等を必ずご確認ください。
用意するもの
- ベンジン
- 柔らかい布かガーゼ
- タオル(汚れても良いもの)
- 中性タイプの洗濯洗剤
- バスタオル2枚
- 洗濯ネット
- 着物用のハンガー、衣紋掛け(物干しで代用できます)
- アイロン、アイロン台、霧吹き
下準備
- 着物の衿をざっくりと縫い止めるか安全ピンで仮留めにしておきます。洗濯による型くずれを防ぎましょう。
- ベンジンは揮発性で刺激のある成分が空気中に飛び散ります。必ず窓をあける等して換気してください。
- 作業中には火器類の使用をすべて中止しましょう。ベンジンが引火性なので、火事の恐れがあります。
- ベンジンの使用で色落ちなどが起きる可能性があります。共布・裏部分等を使用して、色落ちテストを事前に行うことをおすすめします。
シミ抜きの手順
- 汚れても良いタオルを敷いておく。
- 着物をタオルの上に広げる。
- 柔らかい布にベンジンをしっかり染み込ませる。
- 布でシミの部分を軽く叩き、汚れを溶かして落とす。
- 汚れが落ちたら周辺部も軽く叩いて、輪郭をぼかす。
- シミ抜きした部分をすぐに水で濡らす。
- 中性洗剤を水で薄めてから、シミがある部分につける。
- 指でやさしく馴染ませて、水ですすぐ。
- 汚れをよくチェックする。汚れが見えなくなれば仕上げ洗いに進む。
- 洗面ボウル等に水をためて、中性洗剤を適量溶かす。
- 着物を畳んで洗濯用ネットに入れ、シミがある部分を表側に出しておく。
- 畳んだまま着物を10)の洗剤液に漬けて、両手で押すようにして優しく洗う。
- 3回程度水をとりかえて濯ぐ。
- 着物をネットごと洗濯機に入れて、40秒程度脱水させる。型崩れが不安な場合には省略してOK。
- ネットから着物を出し、バスタオル2枚で挟んで残った水分を吸い取る。
- 着物用ハンガーにかけて、直射日光にあてずに自然乾燥させる。
- アイロンで仕上げ、形を整える。
※ベンジンで強くこすったり、同じ箇所に繰り返しシミ抜きを行うことはやめましょう。摩擦によって表面が傷み「スレ」が起きることがあります。
自分で落とせない混合性汚れもある?
着物についた混合性汚れの状態や着物の種類によっては、家で自分でシミ抜きができないことがあります。
水洗いができない着物
正絹(シルク)の着物等は、水を使ったシミ抜きや水洗いができません。そのため、ご家庭でのシミ抜き対処だけで混合性の汚れを完全に取り除けません。例えば振袖・留袖等の礼装用着物は、正絹であることが多いです。
乾いた汚れ
時間が経って乾いてしまっている汚れは、繊維にしっかり定着しているため、家で落とすことができません。自宅でシミ抜き対処ができるのは、汚れを付けてから2~3日程度までと考えた方が良いです。
後から浮いてきたシミ
シミ抜きを忘れていたり、混合性汚れの中の油性または水性汚れのいずれかが取り切れていないと、半年~1年程度経って、後からシミが浮き上がってくることがあります。これは汚れが酸素と結びついてできる「変色シミ(酸化シミ、黄変)」です。酸化してできた変色シミ(黄変)は、ご家庭では対処ができません。
色素が多いシミ
ぶどう果汁を使っている食品、ワインを使ったステーキソース等、色素成分が多いシミは定着率が強く、早い段階で繊維を染めてしまっていることがあります。このような汚れはできるだけ早く専門店に相談しましょう。
混合性汚れはクリーニングで落ちる?
「丸洗い」では汚れが落ちきらない
一般的な着物クリーニングである着物丸洗い(ドライクリーニング)で落ちるのは、混合性の汚れの中でも油成分の部分のみです。水性汚れの成分はドライクリーニング(石油溶剤)では溶かして落とせないので、汚れがそのまま残ってしまいます。
パッと見には見えなくなっても繊維に汚れが残っていると、後から「変色シミ」になって浮き上がってきてしまうのです。
「シミ抜き」や「黄変抜き」が必要
着物についた混合性汚れをキレイに落とすには、手作業による「シミ抜き」が必要です。また古くなってしまっている酸化シミの場合だと、漂白作業を含めた「黄変抜き」が必要となることもあります。
いずれにしても、着物に強いお店に相談することが大切です。一般的な洋服向けのクリーニング店だと、混合性汚れは「落ちない」と断られてしまうことがあります。様々な対処ができる着物専門のクリーニング店に相談をしましょう。
おわりに
着物に付いた混合性汚れをシミ抜きするには、油性と水性の両方の汚れをしっかりと落とす「ていねいさ」が必要となります。ただあまりにも汚れを落とそうと力を込めてしまうと、表面にダメージがかかって、毛羽立ったり白っぽくなってしまう可能性もあるので、十分に注意してください。
また混合性汚れにベンジンだけで対処して、水洗いをしないのは厳禁です!後から水性汚れの成分が変色してしまうと、専門店でももう対処ができない……というケースも多々あります。対処方法がわからない場合等には、早めにお店に相談をしてくださいね。