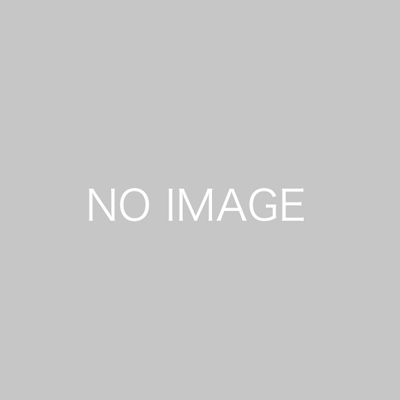七五三着物を着た後のお手入れはどうしていますか?「脱いだまま吊るしてしまっている」「七五三着物の汚れをどうしたらいいかわからなくて困っている…」こんな人も多いかもしれませんね。
七五三着物は着た後の適切なアフターケアや保管で「キレイの長持ち度」がまったく変わってきます!高価で大切な七五三着物をダメにしないように、適切なお手入れとアフターケアを行っていきましょう。

1.七五三着物の汗抜きをする
七五三着物を着たあと、できるだけ早く行ってほしいのが「汗抜き(あせぬき)」です。着物の汗抜きとは、付着した汗の成分をできるだけ取り去るアフターケアのことを言います。
小さなお子様は、大人よりも体温が高めです。そのため汗をかきやすく、七五三着物にはたくさんの汗が付着します。この汚れを残したままで七五三着物を保管すると、数年後の着物の変色(黄変・酸化シミ)を作る原因となります。
一般的な洋服と同じで、汗の汚れは時間が経てば経つほど取れにくくなっていきます。キレイに七五三着物を保管するために、早めに汗抜きのお手入れをしましょう!
ご家庭でできる汗抜きの方法
用意するもの
- 柔らかいタオル2~3枚(白または色の薄いもの)
- バスタオル
- 着物用ハンガー
- バスタオル等の大きめのタオルを下に敷いておきます。
- 七五三着物を裏側を上にして広げます。
- 柔らかいタオルを水またはぬるま湯に浸して、ギュッと固く絞ります。
- 汗をかいた部分をタオルでトントンと叩いて、汚れを移していきます。
- つねにタオルのキレイな面が当たるように、接触する面を替えていきます。
- 乾いたタオルでさらに叩き、水分を吸い取ります。
- すぐに陰干し(2.の項目で詳細説明あり)を行います。
※タオルをゆるく絞ったり、水でビショビショに濡らした状態で作業を行うのはNGです。水分で「濡れた」状態になると、正絹の七五三着物に「水シミ」ができてしまいます。
2.七五三着物を陰干しする
七五三着物を着たあとに欠かせないお手入れのもう一つが「陰干し(かげぼし)」です。陰干しとは、直射日光に当てないようにしながら風にあてて、衣類を干すことを言います。
一度着用した着物には、たくさんの汗や水分が含まれています。これを陰干しでできるだけ飛ばし、、保管中の「カビ」「虫食い」「変色」といったトラブルを防ぐことを目的としているのが「陰干し」です。
※七五三着物の次回の着用予定が無い場合、先に「3」で説明する肩上げ・腰上げを取ってから陰干しをすると、より縫い上げによるシワ等を取りやすくなります。
陰干しの方法
用意するもの
- 着物用ハンガー
※物干しや突っ張り棒等でも代用できます。
まっすぐな棒タイプが理想的です。
洋服用ハンガーは型崩れの原因になるのでおすすめできません。
- 七五三着物を和装用ハンガーにかけます。
- 直射日光の当たらない場所に干します。
- 湿気が少ない時期であれば窓をあけて換気をします。雨が降っていたり湿度が高い場合にはエアコンをかけて除湿してください。
- 扇風機やサーキュレーターの弱風を当てても良いです。匂いを飛ばす時にも効果的です。
- 着物の湿り気等の状態に合わせ、1日~3日程度干します。
※ガラス窓越しであっても、日光が当たる場所には七五三着物を干さないようにしましょう。長時間干している間に染料が紫外線で分解されて「色あせ」が起こります。
3.七五三着物の肩上げ・腰上げをほどく
七五三着物は縫い上げ(肩上げ・腰上げ)をしてあります。長期間の保管の前には、この縫い上げ(肩上げ・腰上げ)をほどきましょう。
肩上げ・腰上げとは?
肩上げ(かたあげ)は、肩の部分をつまみ上げるようにして縫ってあるサイズ調整のこと。腰上げは腰の部分を同じように縫い上げてあります。
肩上げ・腰上げは「いつかこの縫い上げを取って、着物を大きくして着るほどに体が成長しますように」という祈りをこめた縁起物です。そのため、七五三着物には必ず肩上げ・腰上げが施します。
家に保管していた七五三着物を使う場合には、自宅で縫い上げを行うのが一般的です。呉服店や百貨店等で七五三着物を新規購入した場合には、肩上げ・縫い上げした状態でお手元に届いています。
縫い上げをほどかず保管すると?
肩上げ・腰上げをそのままにして保管すると、次のようなデメリットが発生します。
1)シワが取れにくくなる
縫い上げを早く外しておけば、そこまで強い折りシワは付きません。次回には軽くプレスをすれば、その時に着るお子様の体の大きさに合わせて、またキレイな状態で縫い上げを作ることができます。
しかし肩上げしたままで着物を保管すると、クッキリと強いシワ(折りクセ)が残ってしまいます。プレスしてもシワが取れず、七五三の再使用ができないケースもあるのです。
2)カビや虫害・変色が発生しやすくなる
肩上げ・腰上げで縫い合わせた部分には、他の部分より湿気がこもりやすいです。それだけ、カビ・虫害(虫食い)等のリスクが上がります。また肩上げを数年後にほどいたら、その部分だけが変色していた…といったケースも珍しくありません。
七五三着物をできるだけキレイに保管するには、縫い上げ(肩上げ・腰上げ)を外すプロセスが必要なのです。
すぐ着る予定がある場合には?
七五三着物の着用予定が近くに迫っている場合には、肩上げ・腰上げはほどかないでOKです。例えば「11月の七五三に着物を着て、年が明けたらお正月にもう一度着物を着る」といった場合ですね。この場合には縫い上げ(肩上げ・腰上げ)をほどかず、お正月にそのままもう一度着られます。
しかし着用予定が一年以上先の場合には、縫い上げをほどいておいた方が良いでしょう。お子様の体の成長は早いので、現在の縫い上げ(サイズ調整)のままででは一年後にサイズが合わなくなる可能性の方が高いです。
4.七五三着物の汚れをシミ抜き・クリーニング
七五三着物にシミや汚れを見つけたら、できるだけ早く対処することが大切です。七五三着物のしみ抜き・クリーニング対処について解説します。
七五三着物の汚れの原因を確認
七五三着物のシミ抜きを適切に行うには、シミの原因と性質を特定することが大切です。
1)水溶性のシミ・汚れ
水溶性のシミ・汚れとは、水に溶けるが、油には溶けない汚れのことを言います。
例
- 汗
- お茶、ジュース
- おしっこ
これらの水溶性汚れをご家庭で落とすには「水洗い」が必要です。洗える着物であり、シミが新しいものならばご家庭でもシミ抜き対処ができます。ご家庭で洗えない着物の場合には、シミ抜きできません。すぐにクリーニング専門店に持ち込みます。
2)油溶性のシミ・汚れ
油溶性のシミ・汚れとは、油(溶剤等)に溶けるが、水には溶けにくい汚れのことを言います。
例
- 皮脂の汚れ
- ファンデーション汚れ
- オイルのシミ 等
シミ範囲が小さく、新しい汚れであれば、ベンジン等の溶剤を使ってご家庭で汚れ取りができるものもあります。※ただし「広範囲の汚れ」「古い汚れ」はご家庭用の溶剤では落ちません。
3)混合性のシミ・汚れ
混合性のシミ・汚れとは、油溶性・水溶性の両方の性質を持つ汚れです。まず油(溶剤等)で油溶性の汚れを落とし、それから水洗い等で水溶性汚れを落とします。
例
- ラーメンのスープ
- 母乳のシミ
- 牛乳の汚れ 等
混合性汚れをご家庭で落とし切るには「溶剤でのシミ抜き」と「水洗い」の両方が必要です。洗える着物であればご家庭でもシミ抜き対処できるものもあります。ご家庭で水洗いできない着物の場合には、シミ抜きできません。すぐにクリーニング専門店に持ち込みます。
4)不溶性のシミ・汚れ
不溶性のシミ・汚れとは、水にも油(溶剤)にも溶けない汚れのことを言います。
例
- 泥ハネ
- ゲルボールペンインクの汚れ
- 墨、墨汁の汚れ
- ペンキの汚れ
- サビの汚れ 等
不溶性汚れはご家庭では一切の対処ができません。また一般的なクリーニング店でも「シミ抜きできない」とお断りになることが多いです。七五三着物に不溶性汚れが付いた場合は、できるだけ早く着物専門のクリーニング店に相談しましょう。
七五三着物の素材を確認
七五三着物が着用後にシミ抜き等のお手入れができるかどうかは、着物の素材によっても変わってきます。
- 正絹(シルク)の着物の場合:水洗い等、水を使ったお手入れはできません。水を使うとその部分が縮んでしまって元に戻らなくなります。
- ポリエステル着物の場合:ポリエステル着物は原則的に水洗いでのお手入れは可能です。ただし「刺繍」「縫い付け」「プリーツ加工」等の加工がある場合、ポリ着物でもご家庭で洗えない場合があります。洗濯表示をよく確認しましょう。
- ウォッシャブル加工着物の場合:東レ「シルック(R)」のような、ご家庭で洗えることを目的とした加工が施されている製品です。ご家庭での水を使ったシミ抜きや全体洗いをすることができます。
なお、昔の着物の場合には洗濯表示・素材表示がないことも多いです。この場合、七五三着物(礼装用のフォーマル着物)は、ほぼ「シルク(正絹)」だと考えて扱いましょう。
七五三着物のシミ抜き方法<洗えない着物の場合
洗えない七五三着物の場合、次のような条件を満たした汚れであれば、ご家庭でシミ抜き等の対処ができる場合があります。
- 汚れが「油溶性汚れ」である(水をほぼ含まない)
- 付いたばかり(1週間程度)の汚れ
- 範囲が1センチ以下の小さなシミ
- 色素が少ない(口紅等の色素汚れは色が広がるためNG)
用意するもの
- ベンジン(クリーニング用)
- 柔らかい布、またはガーゼ
- タオル(白または薄色、捨てても構わないもの)
- 着物用ハンガー
シミ抜き前の準備と注意事項
- ベンジンは揮発性で、吸い込むと刺激性があり有害です。作業中は窓を開けるか、換気扇を回して換気します。
- ベンジンは引火性です。ストーブ、コンロ、ライター、マッチ等の火器類の使用はすべて作業中は禁止です。
- 染料・生地の種類によっては、ベンジンによって色落ち・変色が起きる可能性があります。共布等を使った事前の変色テストをおすすめします。
七五三着物のシミ抜き手順
- 床・テーブル等にタオルを敷きます。
- 着物のシミがある部分を広げます。
- 柔らかい布(またはガーゼ)にベンジンをたっぷりと染み込ませます。4.汚れの部分をガーゼでトントンと軽く叩きます。
- 汚れが下に落ちていくので、タオル・ガーゼの面を動かしながら、常にキレイな面が当たるようにしつつ作業を続けます。
- 汚れが取れたら、もう一度ベンジンをたっぷり染み込ませます。
- ベンジンで濡れた境目をぼかしこんで広げ、輪郭がわからないようにします。
- 着物用ハンガーに着物をかけて干します。
※ベンジンのシミ抜きでは、強くこすったり叩いたりはNGです。「スレ」という表面の毛羽立ち、色落ち、変色等の原因になります。
※汚れが落ちきらない場合には無理にシミ抜きを続けず、すみやかに専門店に相談しましょう。
※ベンジンの「ぼかし」が不十分だと輪染みができます。七五三着物でいきなりベンジンを使うのではなく、普段着着物、普段着洋服などでベンジンの扱いを何度か練習することをおすすめします。
七五三着物のシミ抜き方法【洗える着物の場合】
ご家庭で洗える七五三着物の場合は、対処できるシミの種類の範囲が広がります。
- 汚れが「水溶性」「油溶性」「混合性」のいずれか
- 水溶性・混合性の場合は付いてから3~4日以内のもの
- 色素が比較的少ないもの
用意するもの
- 中性タイプの液体洗濯洗剤
- 柔軟剤
- 洗濯用ネット
- バスタオル2枚
- 着物用ハンガー
- 安全ピンまたは針・糸
- アイロン、アイロン台、霧吹き、あて布
※汚れの原因が「油溶性」「混合性」の場合は、この他に上の「洗えない着物のシミ抜き」で用意するものも準備します。
シミ抜き前の準備
家で着物を洗うと「衿元」が型くずれしやすいです。針と糸を使って、カンタンに縫い止めておくことをおすすめします。難しい場合には、安全ピンを使ってもOKです。
七五三着物のシミ抜き手順
- 油溶性・混合性のシミの場合は、事前に「洗えない着物のシミ抜き」と同じようにベンジンでのシミ抜きを行い、油汚れを溶かしておきます。
- 七五三着物を、シミ・汚れがある部分が表に出るようにして畳んでおきます。
- 洗面器などに水を入れて、中性洗剤を適量入れて溶かします。
- 七五三着物を漬け込みます。
- 汚れが気になる部分に洗剤原液を少量付けて、優しく振り洗いをします。
- シミ・汚れが取れたら、全体を上から押すようにして押し洗いをします。
- 水を2回取り替えてよくすすぎます。
- 畳んだ状態で洗濯ネットに入れて、洗濯機で30秒程度脱水させます。(省略してもOK。脱水させすぎるとシワ・型崩れの原因になります。)
- バスタオル2枚で着物を挟み、軽く叩くようにして残っている水分を吸い取っていきます。
- 着物ハンガーに着物をかけて形を整え、陰干しして乾かします。
- アイロンで形を整えます。
※ワイン、ぶどうジュース、コーヒー等の色素の多いシミについてはご家庭での対処が難しいです。できるだけ早く専門店に相談することをおすすめします。
七五三着物をクリーニングに出す場合
次のような場合には、七五三着物をクリーニングに出し、シミ抜きや丸洗いをしましょう。
自分で対処できないシミがある → シミ抜き
- シミが古い
- シミの範囲が広い
- シミの原因がよくわからない
- シミの色素が多くて取れなそう
- 自分でしみ抜きするのは不安 等
礼装用(フォーマル用)の七五三着物の場合、できれば汚れ・シミが見つかり次第、専門店でシミ抜きをしてもらった方が安心です。専門店でも対処が早い方がキレイに汚れを落としきる確率が上がります。「小さいシミかもしれない、ちょっと変かも?」と感じたら、早めに相談することをおすすめします。
次回の着用予定が無い → 丸洗い・汗抜き
- 七五三後の着物着用予定が無い
- 弟や妹に着せる予定がない
- 数年以上は家で保管することになりそう
お正月や卒業式等で着物を着せる予定が無く、今後しばらくは家で寝かせておくかもしれない…という場合には、「丸洗いクリーニング」+「汗抜きクリーニング」で全体のホコリ・チリ汚れと汗汚れをスッキリと落としておくと安心です。
特に汗汚れは長期保管中の変色の元ともなります。次に出した時に「カビだらけ、変色シミだらけ」とならないように、プロの技術でしっかり汚れを落としておきましょう。
【着物専門のお店を選ぶと安心です】
着物の「シミ抜き」や「汗抜き」等については、一般的な洋服クリーニング店だと知識の無いスタッフさんも多いです。着物をクリーニングに出してもただ機械的にドライクリーニングするだけで、落とすべき汚れがキチンと落ちていない…というケースも多々あります。
七五三着物のシミ抜きやクリーニングを依頼するなら、着物を専門に扱うクリーニング店や悉皆屋さん等が安心ですよ。
5.七五三着物を保管する
保管中にトラブルが起きないように、大切に着物を保管しましょう。
タトウ紙に入れて平らに置く
七五三着物はタトウ紙(文庫紙)に包んで、平らに保管するのが鉄則です。吊るしたままで長期保管すると縫い目が傷みます。
タンスや専用袋で保管
七五三着物はタンスの引き出し等に平らに保管しますが、最近では桐たんす・和箪笥の無いご家庭も多いですよね。こんな時にはタトウ紙ごと入れることができる、着物専用の保存袋を使うのも便利です。
防虫剤と防湿剤を忘れずに
着物は「カビ」と「虫食い」の被害に遭いやすいです。着物用の防虫剤と防湿剤(湿気取り)は必ず入れて、定期的に交換しましょう。
年に2回は陰干しを
保管している着物にも、空気中の水分が少しずつ溜まってカビ等の原因になります。年に2回は着物を広げて陰干しし、繊維の中に溜まった湿気を取りましょう。
【お預かりサービスを使う方法も】
「家に着物を置く場所が無い」「定期的にお手入れするのが面倒」という場合には、着物専用のお預かりサービスを使うのも手です。着物のプロが最適な環境で着物を保管してくれるので、次回着用の時まで安心して着物を預けることができます。
当店『着物ふじぜん』でも、クリーニングサービス利用の方向けに着物のお預かりサービスもご用意しています。着物の保管にお困りの時にはご相談ください!
おわりに
七五三着物のアフターケア・保管について解説しましたが、適切なお手入れのお役に立てたでしょうか?『着物ふじぜん』では、着物でお困りのことについて、着物の専門家である”着物ケア診断士”がお客様のご相談を受け付けています。
七五三着物のお手入れやアフターケア、シミ抜き、お取り扱い等でお困りのことがあったら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。